いのうただたか の ちずつくり

12.位置を求める
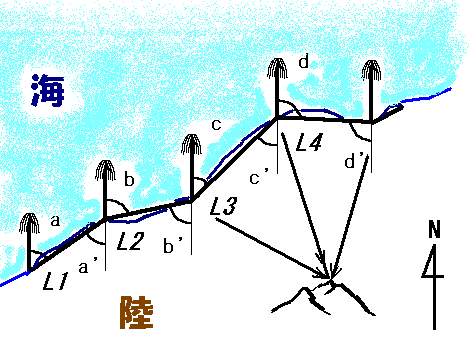
距離は、図のように海岸線や街道(かいどう)の曲がりかどなどに立てた、「梵天:ぼんてん」と「梵天」のあいだのL1、L2、L3を「歩測(ほそく)」や「鉄鎖(てっさ)」などのものさしを使用して測ります。
角度もおなじように、a、b、cを「わんからしん」を使用して、北や南からの角度として測りますが、まちがいをふせぐためa’、b’、c’も測ります。そのとき、aとa’は同じにならなければなりません。
このように距離と角度を測ってする測量方法を、導線法(どうせんほう)といいます。
さらに、まちがいをふせぐため、図のようにいくつかの地点で遠くの山の方向も測ります。こうした測量方法を交会法(こうかいほう)といいます。各点からの方向線が1点で交わらなければなりません。
この角の観測には、小象限儀(しょう しょうげんぎ)という器械も使いました。
やはり、これらの測量結果を「野帳(のちょう:やちょう)」に記入します。
はじめ、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、
11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21
copyright (c) オフィス 地図豆 All right reserved.