シ ー ボ ル ト ま め じ て ん

−シーボルトへのぎもんに答えます−
3.長崎出島で何をしていましたか
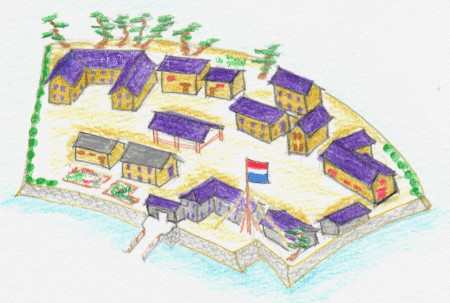
1823年8月、バタビアから長崎出島(ながさきでじま)につきました。
当時、鎖国(さこく:外国との貿易<ぼうえき>や行ききを、せいげんすること)をしていた日本にとって、出島だけが外国の品々や学問(がくもん)、文化に開かれた場所でした。とくに、ここではオランダとの貿易がゆるされていました。
長崎には、そうした西洋の品々を手に入れたい商人(しょうにん)や、文化や学問について知りたい学者などがたくさんきていました。シーボルトにはは、貿易をさかんにするための調査をするというオランダ政府の命令も受けていましたから、出島のオランダ商館(しょうかん)で医師の仕事をしながら、長崎の町のようすや、日本の人々の考え方などを知りたいと考えていました。
ですから、出島でくらすオランダ人のための医師としてすごすとどうじに、出入りする商人や武士、そして、その家族の病気をなおしてあげることで、日本の情報を集めようとします。やがて、出島には良いお医者さんがいることがひょうばんになり、日本人に医学(いがく)や植物学などを教えることも始まりました。
そのご、長崎奉行(ながさぎぶぎょう)から、ゆるしが出て、長崎の町なかで日本人を治療(ちりょう)し、学問を教えるようにもなりました。
さらに、多くの病人を助けたことなどで、シーボルトの名医(めいい:よいおいしゃさん)として、学者としての評判(ひょうばん)が、日本各地に広まりました。
はじめ、 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12
copyright (c) オフィス 地図豆 All right reserved.