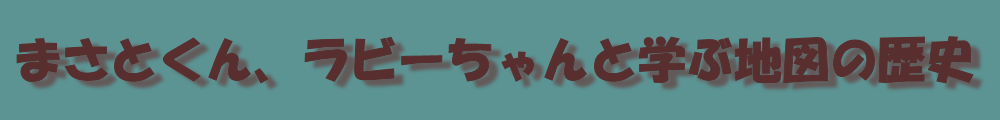
私たちがつかっている地図は、いつごろからあるのでしょう。
ずーっとむかしから、いまのような紙に書かれていたのでしょうか。
むかしの地図に、日本はどのように書かれていたでしょうか。
”まさとくん”と、うさぎの”ラビーちゃん”といっしょに、地図の歴史(れきし)をたどってみよう。
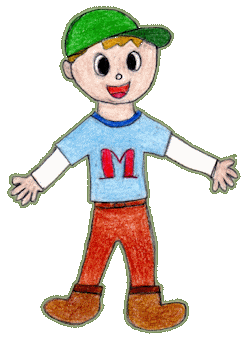
まさとくん
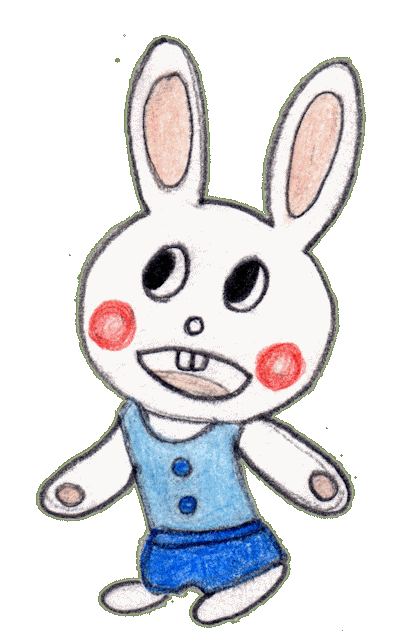
ラビーちゃん
まさとくん、ラビーちゃんと学ぶ地図の歴史表紙へ
おもしろ地図と測量ホームへ
その13 お伊勢参り(おいせまいり)に使った地図
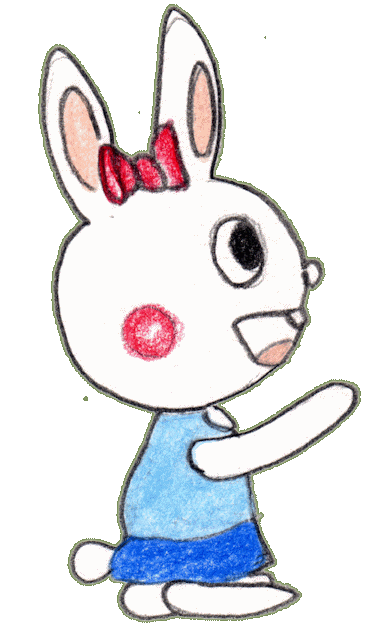 これまでの説明からすると、江戸時代には、国絵図(くにえず)だけしかなかったのですか。
これまでの説明からすると、江戸時代には、国絵図(くにえず)だけしかなかったのですか。
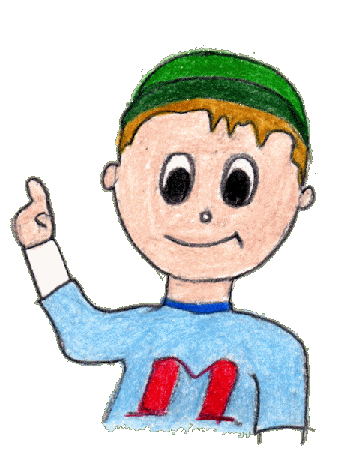 いいえ、そうではありませんよ。
いいえ、そうではありませんよ。
江戸時代になり、国々があんていしてくると、人々の中には、旅に出かけるものも多くでます。
そうなると、そのための日本地図や「道中図(どうちゅうず)」というものが作られ、ふつうの人々にも使われました。
「道中図」は、全体の位置関係はあまり正確ではありませんが、美しく、道すじにそった国々のようすがよくわかるものだった。旅にやくにたつじょうほうも多く書きこまれたものがあって、たくさん作られたんだ。
 それを持って、お伊勢参り(おいせまいり)や江戸への旅にでかけたということですか。
それを持って、お伊勢参り(おいせまいり)や江戸への旅にでかけたということですか。
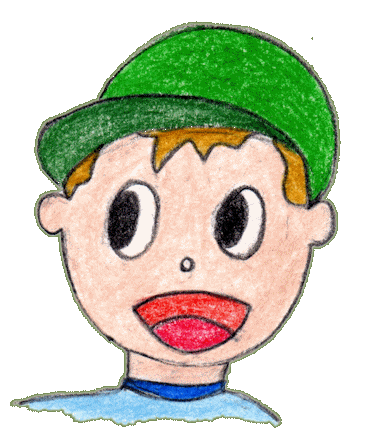 そういうことです。
そういうことです。
街道の地図が巻物になったものや、鳥の目から見たような地図、鳥瞰図(ちょうかんず)のようなものも作られたんだよ。
そればかりではなくて、江戸や京都といった町をくわしくあらわした、カラーの美しい地図も作られたんだ。
それは、江戸では「切絵図(きりえず)」などと呼ばれてね。大名やしきの名前も書いてあって、今の住宅地図のようなものなんだ
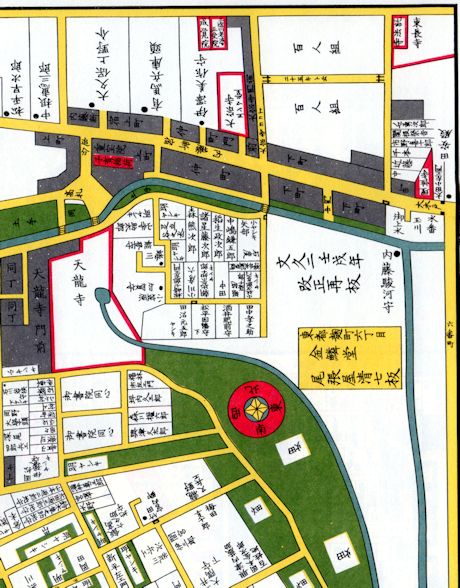
江戸切絵図(1850年)
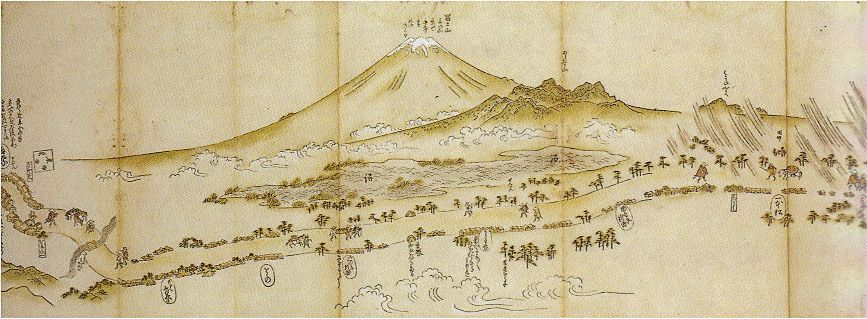
街道をしめした絵図(「東海道分間延絵図」)1690年
 へー、鳥瞰図や住宅地図も、あったんですか!
へー、鳥瞰図や住宅地図も、あったんですか!
もどる
 すすむ
すすむ