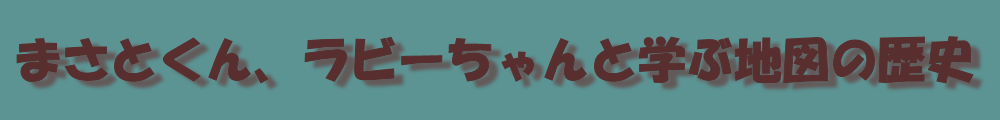
私たちがつかっている地図は、いつごろからあるのでしょう。
ずーっとむかしから、いまのような紙に書かれていたのでしょうか。
むかしの地図に、日本はどのように書かれていたでしょうか。
”まさとくん”と、うさぎの”ラビーちゃん”といっしょに、地図の歴史(れきし)をたどってみよう。
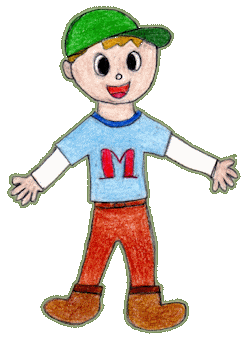
まさとくん
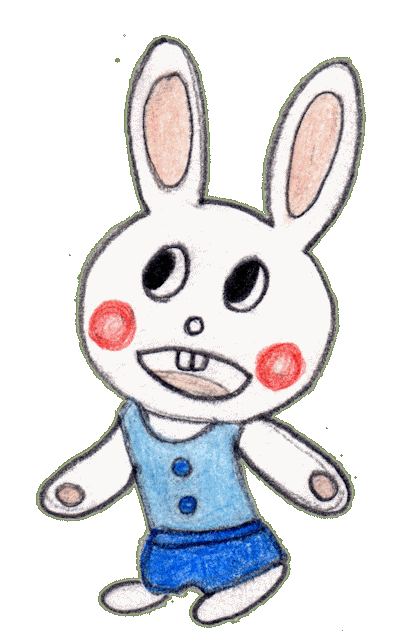
ラビーちゃん
まさとくん、ラビーちゃんと学ぶ地図の歴史表紙へ
おもしろ地図と測量ホームへ
その16 地形図とこれからの地図
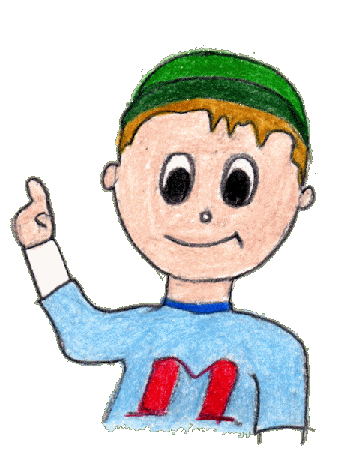 その後、明治の終わりころから大正、昭和にかけて日本中で測量(そくりょう)がおこなわれて、地図が作られます。
その後、明治の終わりころから大正、昭和にかけて日本中で測量(そくりょう)がおこなわれて、地図が作られます。
1895年に作り始めて、1924年に日本全国が、ほぼ完成(かんせい)しました。30年近くもかかったということ。
それは、1/50,000という縮尺(しゅくしゃく)の地図で、日本全体で約1,000枚にもなります。
 へー、そんなにかかったんですか。
へー、そんなにかかったんですか。
伊能さんは、20年ほどで作ったのにね。
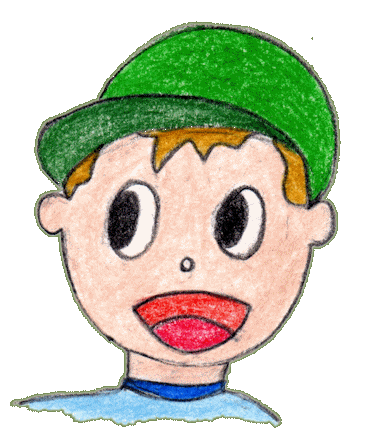 伊能忠敬(いのうただたか)が作った日本全図の中で、一番大きい縮尺の地図は「大図(だいず)」というのがあってね。
伊能忠敬(いのうただたか)が作った日本全図の中で、一番大きい縮尺の地図は「大図(だいず)」というのがあってね。
その縮尺は、1/36,000。
でも、伊能図では、まっ白だった山のおくまで、地図が作られたんだよ。
その後、縮尺1/25,000という地図も作られたんだ。
それは、1910年に作り始めて、戦争(せんそう)などで、とちゅうで休んだこともあって、1983年に、ほぼ終わった。
日本全体ができるのに、70年もかかったことになるね。

1/25,000地形図
 70年もかかったのですか。大変な仕事なんですね。
70年もかかったのですか。大変な仕事なんですね。
でも、その地図は、だれが作ったのですか。
それに、いま私たちが使っている地図や地図帳はだれが作ったのですか。
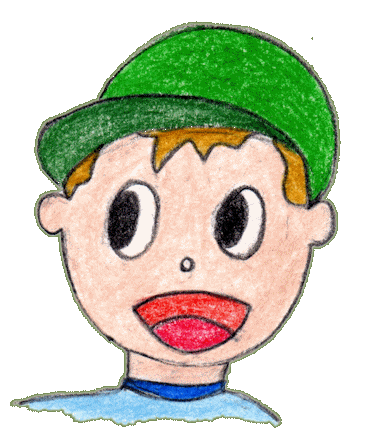 1/25,000や1/50,000の地図は、国土地理院(こくどちりいん)というおやくしょが作っているんだ。
1/25,000や1/50,000の地図は、国土地理院(こくどちりいん)というおやくしょが作っているんだ。
みんなが使っている地図帳は、国土地理院が作った地図をさんこうにして、地図会社などが作ったものなんだよ。
それから、インターネットなどで見る地図は、やはり国土地理院が作った地図や、市役所などが作った地図を、地図会社などが、見やすい形に加工(かこう)したものなんだよ。
さいしょ、地図は土やひつじの皮に書かれたね。
そのごはながい間、紙に書かれてきたんだけれど、さいきんでは、いろいろな地図があるね。
パソコンで見える地図、立体的にあらわした地図、カーナビで使われる地図、けいたい電話の地図などなど。
このあとには、どんな地図ができるのかなー。
それに、町のようすは毎日のように変わるから、国土地理院や市役所などでは、いつまでも地図を作り続けなければならないんだよ
これで、まさとくん、ラビーちゃんと勉強してきた「地図の歴史」を終わります。


カーナビゲーションとの携帯端末の地図
みなさん、さようなら!
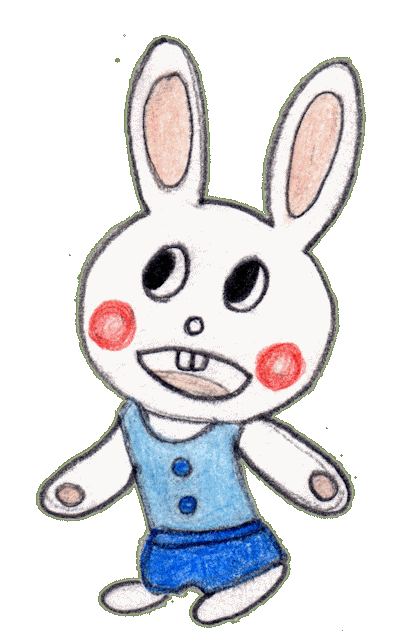
もどる
 さいしょにもどる
さいしょにもどる