地図にかかれた地名から想像して作ったお話をおとどけします。
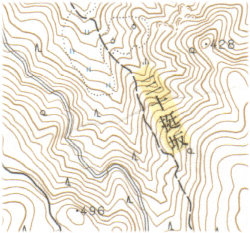
熊本県芦北町三十挺坂(さんじゅっちょうさか) 1/25,000地形図八代7号の4「大関山」
おもしろ地図と測量ホームへ
熊本県 「三十挺坂」
(さんじゅっちょうさか)

戦国時代(せんごくじだい)のことじゃった。国ぐにでは、いくさがたえなかった。
肥後(ひご)の国のとある殿様(とのさま)はな、いくさにそなえて商人(しょうにん)から、”てっぽう”を手に入れることにしたそうな。
てっぽうを買ってくるようにめいれいされた兵(へい)たちは、みなと町の商人から十ちょうのてっぽうを手に入れると、城をめざして道を急いだそうな。
ところが、行き帰りにとおる峠(とうげ)はな、夜になると、とてもぶっそうなところだったんじゃ。だから、たとえ兵であっても、明るいうちに通りすぎたかったんだと。
「暗くなったのー」
「ぶっそうだから、みんな、少し急ごうぞ」
しかし、峠をこえるころにはな、あたりはうすくらくなってしまったんじゃ。
兵たちが、大きな”くすのき”が見わたせるところまでのぼってくるとな、向こうから、たくさんの火が近づいてくるのが、見えたそうな。
「てきの火だろうかの?」
兵たちは、あわててものかげにかくれたと。
「なんだ、なんだ」
「なんの光だろう?」
「となりの国の、てきかなー?」
それははな、きものすがたの女狐(めぎつね)とおおぜいの狐(きつね)をのれつだったそうな。
そして、兵たちは、女狐の美しさに見とれてしまたっんだ。だれかがいった。
「狐のよめ入りだ」
「きれいな、はなよめだのー」
その時のことじゃ。光がまたたいて、兵たちはいっしゅんだけ目がくらんだそうな。そのしゅんかんにおきたのだろうかの。
とにかく、もとにもどった時にはな、買いもとめた十ちょうのてっぽうは、小えだのたばになってしまったそうな。
おどろいた兵たちは、付近をくまなくさがしたんじゃが、てっぽうはどこにもなかったんだと。しかたなく、てっぽうが、ばけてしまったと思われる、木のたばをせおって城へ帰り、殿様に、すべてをほうこくしたそうな。
「そんなばかな話はあるもんか、おまえたちは、お金をほかに使ってしまったのだろう」
おこった殿様(とのさま)はな、兵(へい)たちを、とうげにつれてゆき、とうげの大きなクスの木の下で、うちくびにしたそうな。
殿様は、あたらしい兵に命じて、ふたたび、十ちょうの“てっぽう”を買うことにしたんだと。
ところが、こんどもおなじことがおきたそうな。兵たちは同じように、そのようすを報告したんじゃが、殿様はしんじなかったそうな。
「ほんとうに、狐のよめ入りのれつが!」
「そして、てっぽうが小えだにかわってしまったのです」
「おゆるし下さい」
と、兵たちは、口ぐちにゆるしをお願いしたんじゃがな、殿様は聞き入れてくれなかったんだと。
「おまえたちは、だいじなお金を使って、みなと町で酒を飲み、遊んできたのだろう」
怒った殿様は、こんども兵たちを峠でうち首にしたそうな。
気が静まらない殿様はな、こんどはけらいの兵をつれて、てっぽうをかいもとめに、みなと町に向かったんじゃ。
帰り道、峠に近づき、くすのきが見えてくると、これまでの兵たちが話してきたこととおんなじことがおきたそうな。
それどころか、よーく見ると、はなよめをおともする狐はな、かた足がないものや、かた目のものなど、あちこちに“ほうたい”をまいた狐ばかりであったんじゃ。
そして、そのうしろには、うち首にされた兵の顔も見えたそうな。
「わー」
「たすけてくれー」
殿様も、ともの兵もな、いちもくさんに、そしてころげるように峠(とうげ)を下りたそうな。しかし、走っても、走っても城にたどりつかなかったんだ。
すっかりつかれきった殿様と兵たちは、坂道のとちゅうに、へたりこんでしまった。
ところが、不思議なことに、そこは大きなくすのきのある峠じゃった。
目の前には、たくさんの骨(ほね)がつみ上がっていた。
おどろいてたおれこむ殿様と兵たちを、金色に光る目をもった女狐と、きずついた狐たちが取りかこんだんだと。
「ゆるしてくれ、私がなにをしたというのだ」と、殿様がいうと、女狐(めぎつね)が続けていったそうな。
「なんにもしてないというのですか」
「てっぽうをもとめて、なにをしようとしているのですか」
「... ...」
「人間たちのいくさで、どれだけ多くの狐が、いや動物たちがしんでしまったか。そして、あなたは、またいくさを始めようとしているのですね」
光る目の女狐がいった。
取りかこむ狐たちは、いくさのまきぞえできずついたものや、なくなったものの亡霊(ぼうれい)じゃった。
それぞれの目が光りかがやき、そして、てっぽうをはこぶことや、いくさを止めるように、せまった。
亡霊(ぼうれい)狐たちが、殿様と兵たちにせまってきた。
「いくさをやめろー!」
「友だちをかえせー!」
亡霊(ぼうれい)は、ふるえる殿様と兵たちの上からもせまり、光る目は血(ち)のように赤くかがやいた。
「たすけてくれー」
「たすけてくれー」
「わかった、ゆるしてくれ」
殿様も兵たちも、体を二つにおって、手を合わせてなんどもも、なんどもさけびつづけたんだと。
「いくさをやめろー!」「友だちをかえせー!」の声は長くつづいた。
そして、「いくさをやめろー!、友だちをかえせー!」という声が、小さくなったころには、しだいに夜が明けてきたそうな。
買いもとめたはずのてっぽうはな、小えだになり。そこには、ほんの少しじゃが、赤い血とけものの毛がついていたそうな。
すっかりかいしんした殿様はな、くすのきのある峠(とうげ)に、兵をとむらう五輪塔(ごりんとう)と、狐の形をした石の塔(とう)を立てて、二度といくさをしないとちかったんだと。
そのご、村々は大きないくさにまきこまれることもなく、村人は平和にくらし続けたんじゃ。
それからというもの、あの大きな“くすのき”がある峠までの坂道を、「三十ちょう坂」とよぶようになってな、悪い心をもったものがとおると、赤い目の狐があらわれるといわれていると。
もどる
 すすむ
すすむ