地図にかかれた地名から想像して作ったお話をおとどけします。
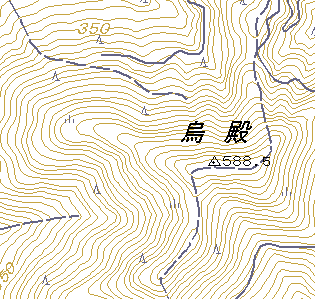
愛媛県西予市宇和町烏殿(からすでん) (1/25,000地形図松山8号の4「卯之町」
おもしろ地図と測量ホームへ
愛媛県 烏殿と烏家老
(からすとのと からすかろう)

この村をおさめる大殿(おおとの)さまは、とても心のやさしい人じゃった。
雨が多くて、農作物のなにもかにもが不作(ふさく)のときには、もしものためにたくわえておいた米を、村人にわけあたえるような大殿じゃった。
それだけでなく、不作のときには城下(じょうか)を見まわっては、農民(のうみん)や商人(しょうにん)に声をかけ、はげまして歩くような人だったそうな。
ある年のこと、村々はたいそうほうさくになった。殿さまは、ねんぐとして、いつもより多く集まった米の一部を、いつものとおりに、くらにたくわえておくことにしたんだ。
ところが、つぎからつぎへと、はこばれてくるお米で、くらがいっぱいになってな。米蔵奉行(こめぐらぶぎょう)は、このことを上の役人につたえたそうな。
これを聞いた家老(かろう)と若殿(わかとの)はな、大殿さまにはないしょで、あふれた米を売ることを考えたんだと。
さっそく、商人をよび米蔵(こめぐら)からあふれた米を売った家老と若殿はな、そのお金で酒を飲み、歌をうたい、遊びほうけたんじゃ。
ところが、遊びはまいばんのことだから、そのお金もいつしかなくなり、二人は、また相談したんだ。
もちろん、くらの中の米を売ることをじゃ。
夜遊びは、また始まった。
米を売っては、夜遊びをする。また、わるいい相談をするということをくりかえしていた。
でも、悪いことはできないもんじゃな、それをじっーと見ていたものがいた。
くらの東のすみには、大きなシイの木があってな。そこには、この城ができてからずっーとすみ続けるカラスの家族がいた。カラスたちは、出し入れのときに落ちる米を食料にしていたんじゃ。
きせつごとにくりかえされる出し入れでこぼれる米が、子カラスのえさとして、きちょうなものだったんじゃ。
カラスたちは、家老(かろう)と若殿(わかとの)さまのすることを、初めはじっーと見ていたんじゃが、「これでは、米がいっきになくなってしまうぞー」と思うと、こらえきれなくなってな。米のはこび手をおそうことにしたんじゃ。
ところがじゃ、くらだしは、日ぐれから始まるから、鳥目のカラスにはよくみえない。こうげきはうまくいかなかったと。
なん日目かの夜になると、またくらが開かれ、米がはこび出された。
「もうー、がまんができないー」と、カラスたちは、米のはこび出しのちょうほんにんである家老と若殿を、ひるまのうちにおそうことにしたんじゃ。
シイの木にすむカラスが、くらのわきで相談をしている二人を見つけると、家族全員でおそった。
おそわれた二人は、意味もわからず、頭を手でかくしては、右へ左へとにげまわっての、やっとこさ、城の中へにげのびたんじゃな。
そしてよく朝、二人は、なにかむずかゆーい感じがして目がさめたと。顔をあらいにゆき、おけにくんだ水の中をのぞくとな、顔がいつもより黒ずんでいるようであったと。
それでも、その日はなんとはなしにすごしたんだ。だが、きのうの相談が、とちゅうになっていることを思い出した二人はな、またくらのうら手に集まった。
するとまた、シイ木のカラスの家族が、おそってきたんだと。いちだんと強いこうげきに、二人は、おどろいて部屋ににげ帰ったそうな。
よく朝は、つめを立てたいほど顔がかゆくなり、色も真っ黒になってきた、そればかりか、くちばしのようなものがはえてきたんだと。体は人間、頭はカラスのようになってしまったんじゃ。
声さえも、何かガラガラといした感じになってきた。
もちろん、家老もじゃ。
二人はしだいに人前に出なくなり、顔をかくして歩くようになってな。山の城にすまいするようになったんじゃと。
それでも、どこかで顔をみられたのだろうかの、けらいや村人は、それぞれのことを「烏殿(からすとの)」とか、「烏家老(からすかろう)」とよぶようになったんじゃ。
そして、この村の人びとはな、その後もずーとやさしい大殿と若殿さまの下で、しあわせな生活を送ったんじゃと。
どうしてじゃろうな。
若殿さまはな、顔を洗うたびに、くちばしのある自分の顔を見てはの、あのときのことをはんせいして、すぐに、山の城から、ふもとの城にもどったと。
みにくい若殿の顔を見たけらいたちも、村人たちも、わるさをするものはいなくなったんじゃ。
そうなると、若殿のくちばしも、しだいに短くなり、声ももとどおりになったんじゃな。
でも、顔色だけはな、黒くてたくましくなり、心は大殿(おおとの)さまのように、まっ白でやさしーい人になったんじゃと。
いまでは、その二人がすまいしていた山の城があったあたりには、カラスをまつる神社があってな、「烏殿(からすでん)」とよばれているそうな。
もどる
 すすむ
すすむ