地図にかかれた地名から想像して作ったお話をおとどけします。
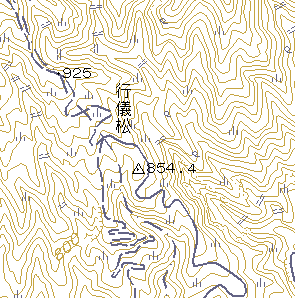
熊本県阿蘇郡高森町行儀松(ぎょうぎまつ)(1/25,000地形図大分15号の4「阿蘇山」)
おもしろ地図と測量ホームへ
熊本県 阿蘇をみはる行儀松
(あそをみはる ぎょうぎまつ)

たくさんのむかしのことじゃった。
阿蘇(あそ)の南のふもとに、木こりたちがくらしている村があった。
そのころの阿蘇山は、雲の先にあるてっぺんから、村のものがすむふもとまで、うっそうとした木におおわれた山であったんだと。
その中の、いっけんの家に”あすま”という子がいてな。お父さんやお母さんに愛されて、元気にそだてられていたんだと。
十歳になると、村のものといっしょに阿蘇山へ上っては、木を切り出し、材木にする、木こりの仕事をてつだうようになったそうな。
まい日のぼる阿蘇への道の入り口には、松の木があってな、その下には小さなほこらがあったんだ。
あすまは、まい日その前にくると、きまっておまいりをしたんだと。
「お父さん、お母さんが病気をしないで、いつまでももと気でくらせますように」とね。
そうしたある日、近くの松(まつ)が、とつぜんしゃべったんだと。
「あすまくん、阿蘇山の松は、のこり少なくなった。まい日のように友だちがいなくなる。
きみが、お父さんやお母さんのことを心配するように、ぼくはちょうじょうに近いところにすんでいる、私のお父さん松やお母さん松が心配だ。どうか、これ以上、木を切るのをやめてほしい。それとも、若い木がそだつまで、切り出しを休んでほしい。」とね。
もっともだと思ったあすまは、村の木こりなかまに、このことをつたえた。なん日も、なん回もね。
でも、だれひとりとして聞いてくれる人はいなかった。
「そんなことで、木こりがつとまるか」
「木こりが、木を切り出さないで、明日からどうやって、めしくうだ」と、木こりなかまがいった。
あすまもしかたなく、今までどおり、いつもの道をおうふくして仕事に出かけた。
でも、あの松の下のほこらでは、いつものねがいことがいえなかった。いったとしても、合わせた手の下で小さくつぶやくだけだったんだと。
そばに立つ松の木のさびしそうな顔、かなしい声を聞くのがつらかったからだ。
しまいには、その道をさけて仕事に行くようになってしまったと。
そんなある日、木こりたちは、ついにほこらの松にまで目をつけるようになった。
あすまは、ひっしにていこうした。
「だめだ、この松の木だけは、切ってはいけない。かんべんだから、切らないで!」
あすまのひっしの言葉に、なかまの木こりたちは、しかたなくほこらの松をのこしてまわりの木を切り出してしまったんだと。
そんなある日、あすまが、ほこらの前にくると、ほこらの松(まつ)がいったんだ。
「あすまくんありがとう。ぼくのお父さんはもう切りたおされてしまったけれど、のこされたぼくが、これからまい日、木をふやして、阿蘇を緑いっぱいにする」とね。
「ごめんなさい、なんにもできないで」
あすまは松の木をだきしめて、声を聞き、いっしょにないたんだと。
それから、長い時間がたったいま、ほこらの松はかれてなくなってしまった。
ところが、阿蘇山にのぼる道のとちゅうには、大きな松があるんだな。
そして、この大松より高いところには、松の木は一本もはえていないのだが、それより低いところには、松がたくさんのこっているんだと。
ほこらの松は、あすまに話をしてからというもの、まい日、夜になると小さな松のえだをそこらじゅうにに飛ばしたんだ。
そのえだが飛んだ先に、小さな松の木が、つぎつぎ生え、そだち、いまのようになった。
そして、いのちがつきるころ、さいごに飛ばしたえだが、この大松になったという。
それからというもの、村のものは、この大松のことを、ずーと「行儀松(ぎょうぎまつ)」とよんでいるんだと。
なんで、「行儀松」だかって、それはね、村のものがむやみに木や草を切らないように、高いところから、村人の行いをみはっているからなんだ。
あすまは、どうしたかって。
木こりの仕事は、まもなくやめて、木のおさらなどを作る職人(しょくにん)になってな、それこそ行いのよい大人になって、しあわせにくらしたんだと。
もどる
 すすむ
すすむ