地図にかかれた地名から想像して作ったお話をおとどけします。
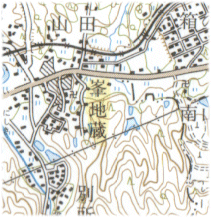
石川県鳳珠郡能登町十郎原(じゅうろうはら)1/50,000地形図輪島8号「宝立山」
おもしろ地図と測量ホームへ
石川県 「大飯くらいの十郎」
(おおめしくらいのじゅうろう)

そのむかし、能登(のと)のおく深くに、ひときわ高い山があったと。その山は、能登から海をへだてて見える、となりの国の越中(えっちゅう)の立山(たてやま)よりも高い山であったそうな。
そのころの能登はというと、冬になると北風が強ーくふいて、それがこのびょうぶのように立ちはだかる大山にあたってな、北からは海風、山からは“大山おろし”と、村人はおおじょうしていたんだと。
そのふもとの村に、十郎という若者がいての、それはそれは大飯(おおめし)ぐらいであったが、たいそう力もちでもあったんだと。
でも、力持ちというのは、十分に食べ物があったときのことで、はらをすかしているときは、たんなる“でくの坊(でくのぼう)”でしかなかったんじゃ。
十郎のオカアはな、その大飯くらいに、ほとほとこまっていたんじゃ。
特に、食べ物が少なくなる冬には、「はらすいたア、オカアなんか食べ物ないか」という声ばかりで、はたらこうとしない十郎に、ほんとうにこまっていたそうな。
こまったオカアはな、村の入り口の小さな”ほこら”に、まつられた原の神様におねがいしたそうな。
「原の神様、どうか十郎の大飯くらいをなおしてくんろ。それとも十郎に十分の食べ物がさずかるようにしてくんねえかのお」と。
ある日、はらをすかしてねていた、十郎のまくらもとに、手のひらにのるほどの小さーな”てんぐ”があらわれての、耳もとでこういったんだと。
「十郎よ、はらいっぱい飯(めし)が食いたいかの。」
もちろん、十郎はこういった。
「おおー、はらいっぱい飯くいたいだ。」
小さなてんぐは、耳のそばで、続けていったそうな。
「それならな、良いことをおしえてあげようぞ。能登(のと)の大山の下にはな、食べ物がたくさんうめられている。ほり返してみなされ、きっと、はらいっぱいになろうぞ。」
はらをすかした十郎は、のこりの力をふりしぼって大山にのぼると、これも力をさらにふりしぼって岩をほり返したんだな。そうすると、下から食べ物が出てきたんだと。
その食べ物を食べると、耳もとにこんな声が聞こえたんだと。
「岩の下には、食べ物がたくさんうめられている。ほり返せば、はらいっぱいになろうぞ」
少しはらがふくらんで力がついた十郎は、こんどは山の大岩を持ち上げてはな、北の海めがけてなげたんだと。なんどもなげていると、また下から食べ物が出てきたんだと。
その食べ物を食べ終わると、また、小さなあの声が聞こえたそうな。
「岩の下には、食べ物がたくさんうめられている。ほり返せば、はらいっぱいになろうぞ。」
食べ物という言葉に、がまんができない十郎は、岩山を持ち上げては、海になげすて、またまた食べ物を手に入れたんだと。
これをくりかえしていた十郎も、日がくれるころになると、さすがにつかれての。大岩を持ち上げて遠くへなげつけようとしたんだが、足をすべらせて、大岩はとんでもないところに飛んでいったんだと。
こうして、十郎が日ぐれまで大岩をちぎってはなげしているうちに、あのびょうぶのように立ちはだかる大山はあとかたもなくなって、平らになったんだ。
今では、大山のあったあたりを“十郎原”とよんでいて、“大山おろし”の強い風もふかずに、村人はよろこんでいるそうな。
そして、あの十郎が投げた大岩ののこりが、輪島(わじま)の北のおきにある「七ツ島」なんだと。
さらに、さいごになげそこなった大岩はな、東の珠洲(すず)の海岸にある「見附島(みつけじま)」なんだとさ。
十郎は、どうなったかって。
そうださな、すっかりはらいっぱいになった十郎はな、村へ帰ると春までねていたそうな。
そして、その年から、村には強い風もふかず、たくさんの作物が取れるようになってな、十郎はよくはたらき、村人からもしたわれてな、一生はらへらすこともなく、くらしたそうな。
もどる
 すすむ
すすむ