地図にかかれた地名から想像して作ったお話をおとどけします。



茨城県つくば市弥平太(やへいた)、五斗蒔(ごとまき)、鬼が窪(おにがくぼ)1/25,000地形図水戸15号の2「上郷」
おもしろ地図と測量ホームへ
茨城県 「弥平太村の五斗蒔」
(やへいたむらのごとまき)
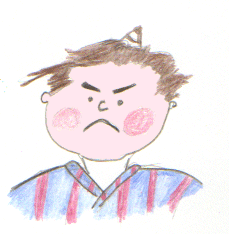
そのむかし、つくば山が、すぐ近くに見える、ある村の南のはずれに、いっけん家があっての。
そこに頭のてっぺんが、ちょっとだけもりあがった、元気な子どもがすんでいての、名まえを、弥平太(やへいた)といったんじゃ。
弥平太には、おっとうも、おっかあもいなかった。
弥平太が、いつからこの村の、この小さな家に、すむようになったのかは、村人のだーれもが知らないことだった。
弥平太は、同じ年ごろの子どもたちと遊ぶこともなく、村の仕事の手つだいをしては、おれいにたべものや、きがえをもらって、静かにくらしていたんじゃと。
さて、あるときから、この地方は天気のわるい日が多くなってな、野菜(やさい)や米のしゅうかくが、少なくなったんだと。
そして、あらそいごとも多くなったそうな。
それを、どこかで見ていたかのように、夜になると鬼(おに)が、村にくるようになってな。鬼たちは大声を出しては、村人をおどろかして、食べ物を持ちさるようになったんだと。
その鬼たちは、つくば山のおく深くにある、どうくつからやってきたんじゃと。

こまった村人たちは、鬼をおいはらおうとして、そうだんをはじめたと。
「たくさんのたべものをわたして、二どと村へこないようにたのんでみたらどうだべ」
「おれたちでさえ、食べるものがないのにか?」
「落としあなを作って、こらしめたらどうだべか」
「そんなことしたら、よけいに、わるさをされるじゃろ!」
「つくば山の神様(つくばさんのかみさま)に、おねがいしたらどうだべ」
「つくば山の神様は、えんむすびの神様だで、むりだっぺ」
村人は、しんけんにはなしあったけれど、これといった、よい考えはうかばなかったんだと。
そうこうしているうちに、秋が近くなってな。
春にうえた“いね”は、やっとこさ、こがね色になって、いねのあたまは少しずつかたむいてきたんだと。
かり入れの日が近づいてきたんじゃ。
みのった米や麦(むぎ)を鬼にもちさられたら、村人はさむい冬がすごせない。
村人は、しんぱいでたまらなかった。
きんじょの村人からそのことを聞いた、弥平太(やへいた)は、村人の前で、こういったんだと。
「ぼくに、いい考えがあります。鬼におねがいしてきます」
「弥平太よ、どんな方法で、おねがいするのかな?」
村一番のおとしよりで、“しょうや”でもある、美祢(みね)じいさんがきいたんじゃが。
「… …」
弥平太は、なにも考えをいわないで、ただ、「ぼくに、まかしてください」というだけだったんじゃ。
美祢(みね)じいさんは、「わけもなく、子どもに、まかせるわけにはできない!」と、弥平太のもうしでをことわった。
鬼をおいはらう、よい考えがうかばない村人と美祢じいさんだったが、もういちどそうだんをはじめた。
でも、村人がそうだんするへやからは、「うーん、どうしよう」という、声がきこえるばかりだった。
「しょうがないなあ、こうなったら弥平太にまかせてみるべか」と、美祢じいさんがいいだした。
「そうさな、たんのでみるべ!」
「たのんでみるべ!」
村人もいった。
美祢じいさんが、弥平太をよんで、おねがいすると、「それでは、三日だけ待ってください」といって、つくば山へむかったそうな。
「たのんでみるべ!」といった村人たちだったが、「子どもに、なにができるじゃろうか」と、あまりしんようしていなかった。
そのごの美祢(みね)じいさんはというと、いつものように、村のだれよりも早おきし、お日さまのほうをむいて手を合わせ、村人のしあわせをおいのりしていた。
そして、三日がたった。
いつもおいのりするお日さまのほうこうを、ふと見ると、にわ木のえだにむすびつけられた紙があった。
おもてには『美祢(みね)じいさんへ』と大きく書かれた手紙じゃった。
じいさんは、いそいで紙をひろげた。 そこには、こう書かれていたそうな。
「美祢(みね)じいさんと村のみなさんへ
鬼たちは、もういたずらをしないでしょう。
ですが、やくそくしてほしいことがあります。
この世には、みなさんから見ると、みにくい顔の鬼人(おにびと)の世界もあることを知ってほしいのです。
鬼人たちは、ふだんは山のおく深くにすんでいます。ところが、この春ごろから、みんさんの村がさわがしいので、鬼(おに)たちは里へでてみたのです。
そうすると、私たちを見ると『鬼だ、鬼だ』とおとなも子どもも、はやし立てたので、わたしたちは、いたずらをはじめたのです。
どうぞ、私たちを見て、『鬼だ、鬼だ』と、さわぐのは、やめてください。
顔や体は、みなさんとちがいますが、やさしい心の鬼もいれば、あたたかい心をもった鬼もいます。
村人の中には鬼人よりも、みにくい心をもった人もいます。もちろん、鬼の世界にもいますが、それは少しです。 鬼より」
美祢(みね)じいさんは、村人を集めて手紙をよみ、鬼人のねがいをつたえたんだと。
そして、あいずの花火を二つあげたそうな。
よく朝になると、つくば山につづく道から、たくさんの鬼人がな、美祢じいさんの村にやってきたんだ。
村人たちは、えがおでむかえ、そしておたがいに手をにぎった。
美祢じいさんの前には、弥平太(やへいた)にそっくりだが、頭のてっぺんに、つのがある小鬼(こおに)がやってきて、いったそうな。
「“しょうや”さん、私たちは、もう、けっしていたずらはしません。ですが、さらにひとつだけおねがいがあります」
「どんなことかね」
「一年に一度、秋のしゅうかくのじきに村人と鬼人(おにびと)が楽しく、すごせるようにしてください。そして、私たちと、つな引きをして、もしも鬼人(おにびと)が勝ったときには、ほんの少しの食べ物を、わけていただけませんか」
「いいとも」
美祢(みね)じいさんは、そう答えながら、小鬼に、「弥平太!」と、こえをかけてみた。しかし、へんじはなかったが、美祢じいさんには弥平太に見えたと。
そして、村のまん中にある橋の上で、つなひきが始まったんだ。
村人からは、うでにじしんのある若者がえらばれ、右へ、左へ“つな”がひかれてな。
まわりで、おうえんする村人も、鬼人もおおさわぎだ。
そして、この年は、鬼人が勝ったんだと。
村人と鬼人は楽しい一日をすごし、鬼人は、お米を五斗(75キロほど)だけもらって山へ帰っていったんだと。
それからというもの、まい年のように秋のしゅうかくのじきになると、鬼人が山から下りてきては、つなひきをするようになったんじゃ。
「どうしてかなー」
つなひきは、いつの年も鬼人の勝ちだったと。
そして、いつの日か、このちほうのてんこうもよくなっての、しゅうかくも多くなったそうな。村には、あらそいごともなくなり、わらい声が多くなった。
そんな年の秋からじゃろうか、鬼人のすがたがみえなくなったんだと。
それからは、村人がふた手にわかれて、つなひきをすることが始まったそうな。
そのころから、美祢じいさんの村は、「弥平太村(やへいたむら)」とよばれるようになってな、つなひきをして、“もちまき”をする近くの橋を「五斗蒔(ごとうまき)橋」、村人の気持ちを知りたいと、鬼の弥平太がすんでいたあたりを「鬼が窪(おにがくぼ)」とよぶようになったとさ。
さて、このあたりの村ではの、今でも村はずれのいっけん家には、かならず鬼人がひとりすんでいて、「村人が楽しくくらしているか、あらそいごとがないか」と、村のようすをみているんだと。
もどる
 すすむ
すすむ